
<最終更新2025.8.20>
こんにちは。外部執筆スタッフの管理栄養士 吉澤裕加です。
新年度に入り約3か月が過ぎました。
大学や専門学校を卒業して初めての職場で栄養士業務を行うようになった管理栄養士・栄養士の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今日は栄養士業務の一環として行う、『喫食調査の実施』についてお話ししたいと思います。
この調査は、マニュアルなどに詳細の内容が示されていないことが多くどのように実施するかの検討に悩む栄養士の方も多いようです。
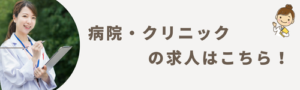
▼目次
嗜好調査の施設の特徴と目的
嗜好調査は、喫食者の嗜好や現在の食事に対する不満等の状況を把握し、献立作成・調理方法・食事提供方法などを見直し、食事に対する喫食者の満足度を向上させることが目的です。
施設や対象者によって、実施する方法はさまざまですが、大きく分けると下記のように分類されます。
*医療機関(病院)…院内で提供する食事に対して喫食者(患者)自身に行う
*保育園・介護施設…喫食者が低年齢層や高齢者の場合には調査への回答が困難な場合、保護者または家族に行う
保育園・介護施設で保護者または家族が回答する場合には、調査内容を工夫して家庭での食事背景(朝食や夕食でどのような食事を好んで食べているかなど)を調査し、献立・調理・食事提供方法などに反映させることが好ましいと考えます。
施設別に見ておきたいポイント
- 病院: 疾患・治療による嗜好変化(味覚低下・食思不振)/食形態の適合(嚥下・咀嚼)/提供温度
- 高齢者施設: 量の個別化(小盛・並・大)/硬さ・一口大のサイズ感/見た目・彩りで食欲喚起
- 保育園: 家庭との味付けギャップ/食具・姿勢の支援/アレルギー配慮と代替メニュー

喫食調査を行うまでの流れ
①嗜好調査の計画
毎年、年1~2回を目安として給食会議にて嗜好調査の実施内容の検討を行う
➁嗜好調査の準備
実施には下記の方法で検討を行う
- 患者または保護者(家族)へのアンケート作成
- 患者・園児・保護者(家族)からの聞き取り
- 残食調査の結果
- 検食簿による結果
- 職員からの聞き取り
アンケート作成は、前年度までの嗜好結果をふまえた内容にすることで比較が行いやすくなります。
対象者へのアンケートだけではなく、日頃の残食量や検食簿等の確認、喫食状況の職員への聞き取りもふまえると、問題点をより抽出しやすく喫食者に合う食事を提供することに繋がりやすいと考えます。
そのまま使える!アンケート設問例
- 味付けの満足度(濃い/ちょうどよい/薄い)
- 主食の量は適切ですか(多い/ちょうどよい/少ない)
- 硬さ・食べやすさ(主菜/副菜/汁物)
- 提供温度の満足度(温かい/冷たいの適正)
- 見た目(彩り・盛付け)
- 苦手食材やアレルギーの配慮について
- 自由記述(食べにくかった・美味しかった・家庭の味との違い など)
設問でのよくある失敗と回避策
- 設問が抽象的 → 5段階評価 + 具体例で回答のばらつきを防ぐ
- 結果だけ共有 → 原因 → 対策 → 結果までをセットで提示
- やりっぱなし → 翌月の残食率や満足度で効果検証まで行うのがベスト
③嗜好調査結果の集計と報告
報告書を作成するときに気を付けること
- 結果に対する結論とそれに対する提案(改善策)
- 提案(改善策)により想定できる効果
- 改善策をどのように実行するか
やりっぱなしにせず、次へ繋げて献立へ反映させていきたいですね。
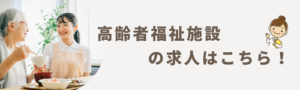
調査の結果、どう反映させていくのか
- 献立
- 切り方、提供温度など調理スタッフへの指示
- 栄養指導・食育教室などの導入
- 食材の変更・業者変更等の検討 等
具体的な行動について検討し周知します。
この時、調査結果を栄養士や調理に携わる調理スタッフだけで周知しがちですが、施設全体のスタッフで結果を共有することで、喫食者へ提供する食事の在り方や考え方を統一できるメリットがあります。
結果から小さく始める改善例
- 量の個別化 : 主食を小盛・並・大で選択制に(残食率↓、満足度↑)
- 硬さの最適化 : 野菜は下茹で時間と切り方の標準写真を共有するとばらつきが減る
- 味の工夫 : 減塩でも満足度が落ちないよう、出汁・香味・酸味で補う
- 提供温度 : 配膳動線の見直しと保温機器の使い分けをマニュアル化

本来の目的を軸に内容を検討
これまで栄養士の方から「喫食調査は、保健所からの監査等で実施の有無を確認される為、行う必要がある」という言葉を何度か耳にしてきました。
しかし、冒頭にも書いたように喫食調査は、食事に対する満足度を向上させることが第一の目的にあります。
本来の目的を軸に置いて食事を検討することで、明確な改善点や再考すべき点を見出すことができます。
栄養士として、特性に応じた食環境を整えられる様、実施施設や対象者に合った内容を検討していきましょう。
まとめ
喫食調査は監査対応のための“イベント”ではなく、現場の声を献立・調理・提供に反映させ続ける仕組みです。アンケート・残食・聞き取り・観察の情報を組み合わせ、原因→対策→効果検証までを一連の流れで回すことで、満足度と栄養価、安全性を同時に高められます。
こうした実践の積み重ねは、管理栄養士・栄養士としての現場対応力・改善力の証明にもなり、スキルアップや転職の場面でも大きな強みになります。
栄養士・管理栄養士の転職はDietitianJob!
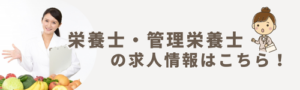
あなたにあった働き方を一緒に探しませんか?弊社のエージェントは全員実務経験ありの栄養士・管理栄養士!
詳しいお仕事の話や、専門性のある質問にもお答えできるので転職後も安心!
弊社では、あなたの経験や強みを最大限に活かせるようにフォローし、理想の職場への転職をお手伝いします。
詳しくはこちらをご覧ください。










