
<最終更新日 2025.9.18>
高齢者施設施設は管理栄養士の活躍の場として代表的ですね。
老人ホームでの管理栄養士の仕事とは?奮闘記シリーズとして現場でのリアルな様子をお伝えいたします。
👉 目次
管理栄養士が高齢者福祉施設で担う仕事
こんにちは、管理栄養士の廣江です。DietitianJobの運営メンバーになる以前は、特別養護老人ホームで12年勤務していました。
高齢者福祉施設での食事は非常に重要です。病院は「治すため」栄養がしっかり調整された食事が重要であるように、高齢者福祉施設では「楽しんでもらうため」「ご利用者の笑顔のため」として食事が位置付けられています。栄養管理ももちろん大切な事ですが、これがご利用者にとって最後の食事になるかもしれない…そう思うと毎日「ああ今日も美味しかった」そう感じていただけるような食事を出したい、それを胸にに日々取り組んでいました。
管理栄養士の主な業務内容
高齢者福祉施設では栄養管理、給食管理、栄養マネジメント計画等の加算・介護報酬への対応がメインになってきます。施設によっては家族への対応や外部への対応等を行う場合もあります。
ご利用者の栄養管理
まずご利用者の栄養状態の把握です。ご高齢の方は何かしらの病歴や既往をお持ちの方がほとんどです。今現在の健康状態、何が必要なのか、何を制限しないといけないのか、どのくらい日常的に食べているのかを把握するのは最も大切な事です。管理栄養士一人では把握することはほぼ不可能なため、ナースやケアワーカー、ケアマネージャーとの情報交換は欠かせません。
また、正しい食事を提供しても食べきれない、消化吸収率の衰えにより食べても太らない、嚥下状態が落ちカロリーが摂れない、口腔内の状況や運動不足、寝たきり、認知の低下…等々、様々な問題があります。その方にとって無理のない、楽しんでいただける食事内容であるかどうか。無理に食べてもらうのではなく、日々穏やかに過ごしてもらえるように……高齢になるとからだの調子は日々変化していくため、定期的な見直しは絶対に必要となります。
献立の作成、給食管理
委託給食会社が入っている、直営での管理をしている、栄養士が配置されているなど施設にもよりますが、献立作成と発注、食材管理は、管理栄養士にとって非常に重要な業務の一環です。
地域柄やご利用者の年代等により嗜好も変わってくるため、嗜好調査やミールラウンド等で喫食率を把握し、献立に反映するのも大切な仕事です。いくら栄養バランスの取れた献立であっても食べてもらえなければ意味がないのです。高齢者は一度食事を抜いただけで健康を崩してしまうこともしばしばあります。
📌関連記事
喫食調査の実施と本来の調査目的について
また、昨今の食材高騰に合わせ、食材や取引業者の選定等を行う場合もあります。米不足の際にはなかなか見つからず、とても苦労しました。
食事形態の調整
高齢者には、咀嚼や嚥下に難しさを感じる方が多く、介護付きの施設であれば通常食よりも食形態を変更した方のほうが多い場合があります。私が実際に働いていた施設は200食程度出したうち常食は2~30食ほどでした。
噛み切るのが難しい方へは一口大刻み食
より難しい方へはソフト食や極刻み食
嚥下が困難な方へはミキサー食、ゼリー食等
多岐にわたる為調理を行う調理担当にも理解をしてもらうことが大切です。均一に仕上げるべきか、多少粒が不ぞろいでもよいのか。なぜここまで形態調整が必要なのか――調理師等に理解してもらうことが大切です。ご利用者が安心して食事を楽しめる環境を整えることは、管理栄養士の責任であり、やりがいのある仕事といえるでしょう。
※極刻み食、刻み食は嚥下困難者に危険と昨今言われますが、実体験としては必要だと感じています。ソフト食では食べた気にならない、食べたくない、こんなものは食事ではない…これは実際にご利用者から言われた言葉です。いくら正しい栄養配分でも食べてもらえなければ意味がないのです。嚥下状態はもちろん、ご利用者の認知度にあったものを提供するのが管理栄養士としての仕事です。刻んだ際に口腔内でばらけないように薄めのとろみでまとめる、煮物の汁やソースにとろみをつけるなどの工夫をして誤嚥のリスクを減らしていました。
介護報酬、加算の為の記録と整理
主には栄養マネジメント強化加算になってくると思います。
施設により退所時栄養情報連携加算や再入所時栄養連携加算になります。
また、経口移行加算、経口維持加算、療養食加算、リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の一体的取り組み等の加算があります。令和6年の介護報酬改定は高齢者福祉施設において栄養管理の重要性がかなりみられるようになってきたと感じます。これらの加算を算定できるように日々記録を正しく行うのは重要な業務です。
ここからは有料老人ホームでの奮闘記になります。
今回は有料老人ホームでの実際の食事形態等のお話です。
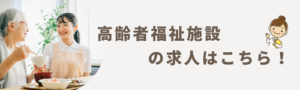
有料老人ホームでの経験談
こんにちは。外部執筆スタッフの管理栄養士 長谷川晴美です。
今回は介護食についてです。
皆様の何かのお役に立てればと存じます。
有料老人ホームの介護食
高齢者福祉施設で提供する食事は何より「安全第一」です。
安全とは、食中毒予防はもちろんのこと、介護施設の場合では、誤嚥(嚥下障害)で命を落とすことや、食べられない場合には低栄養になるので、食事形態に注意を払う必要があります。
お餅を提供しない施設も多いですが、私が勤務していた有料老人ホームでは、餅つき大会、お正月のお雑煮、鏡開きのお汁粉でお餅を提供していました。
看護師も総出で見守り強化をしていましたが、14年の間で詰まらせたかたは一人もいませんでした。
しかし、油断大敵で、大事には至りませんでしたが、普段のパン食やババロア、刺身で詰まらせるかたがいました。
一方、普段は介護食なのに、ご家族の差し入れの寿司や鰻はなぜか食べられる人もおり、これは本当に摩訶不思議でした。
有料老人ホームの介護食の改善
勤務最初の改善の課題は、サラダでした。
生野菜をどう刻んでも飲み込みづらく入れ歯にも挟まるため残していたり、ヘルパーさんがお粥と混ぜて口に運んでいる状況でした。
食べられないものを出しても意味がないというのが率直な感想でした。
サラダの時は、生野菜、茹で野菜、大きさも何パターンか用意しました。
その頃の厨房の所長は、相談しても手間のかかることや新しいことはやりたがりませんでした。
本来、厨房業務全般は委託業者が行うことでしたが、ゼリー食の試作をやってみせることにしました。
といっても私自身も初めての試みなので、適切な介護食の硬さを知るために、まずは、野菜ジュースを介護食用ウルトラ寒天(伊那食品)で固めたものを型抜きして提供しました。
ヘルパーさんに感想を聞いてまわると、「かわいい」や「食べやすい」と好評でした。
その後は、委託業者と話し合い材料費は厨房で、しばらくは手作りゼリーのみ私が作成し、ものによってはミキサーにかけたものにとろみ剤を入れたものや、時代とともに出来あいのソフト食も利用するなど変化していきました。
大塚製薬のあいーと食品が販売されたときは興味深く、営業の人に来ていただき、理事長や各部署長やケアマネージャーにも参加してもらい、試食し導入する運びとなりました。
高価なので、さすがに全員には難しくプラス料金での提供となりました。
金銭的に余裕のある方は亡くなる直前まであいーと食品の方もおられました。
野菜以外にも、肉や魚やフライ系の超きざみ食は生野菜と同様に食べづらいため、そのメニューのたびにその食材にあった美味しいたれを別に用意し、食事介助をするヘルパーさんがとろみ剤でその人にあった硬さにして、かけて提供するようにしました。
粥のミキサー食も食べづらく、ご自身でスプーンを使って食べられる方は、ドロドロでこぼれてしまって食べられないご様子でした。
これには、粘りなくプルプル固められる酵素とゲル化剤の商品を使用しました。
とにかく、問題が上がれば献立会議や栄養ケア会議で対策を考え、そしてやってみる!
の繰り返しが延々続く作業で、情報収集には、ヘルシーフードのイベントの参加や、知り合いのツテで他施設の見学やソフト食の試食も大変有効でした。
提携病院との食形態の共有
保健所の講習会で講義された方が、介護食の名称を全共通にする取り組みをしているが難しいと話されていました。
講習会にいったら、必ず一つは取り入れることにしていたので、その時は、提携病院の栄養士さんに電話し、食事形態の名称を教えてもらい、そろえました。
名称と大きさの一覧表も作成し他職員にも周知しました。
そのことで、退院後の申し送りがスムーズになりました。
食事介助の経験
どんなに手間をかけても、提供する人の協力が不可欠です。
衝撃だったのが、新人ヘルパーさんが薬をすべての食事に混ぜて提供していたのを見た時でした。
さすがに、「あなたはこれを食べられますか?これは先輩がやっていたのですか?」と問いました。
このことで、私自身が、食堂で食事提供の仕事もしていたので、どうしてもお元気な方の対応が優先されていたことを反省しました。
そこで、まわりに相談し協力を仰ぎ、曜日を決めて介護棟に足を運び様子を見にいくことにしました。
また、私自身がヘルパー研修に参加し、一緒に学び、実際に食事介助もしていきました。
自立を促しできるだけ自分で食べられるように、有効な声掛けや一部介助をすること、足の着き方を含めた食べる時の姿勢、食事介助時の目線、スプーンの大きさや材質、口への持っていきかたや角度、介護とは食事介助一つをとっても、個々に合わせた対応が必須で本当に奥が深いものです。
1日3食365日、多種多様な食事形態、個々の尊厳を守ること・・・
生涯、口から美味しく食べられることを実現するために、平穏な日はほぼなく、まさしく奮闘記でした(^^)/
尊敬に値する介護に携わる皆様に、あきらめない心で頑張っていただきたいです。
心から応援しています。
次回は、ノロウイルス対策についてお伝えする予定です。
📌老人ホームで働く管理栄養士の奮闘記 ~ノロウイルスの対応と対策~
まとめ
長谷川さんの体験談からは高齢者福祉施設における食形態調整の難しさが伝わってきましたね。
介護食はおいしさと安全を両立しなければなりません。昨今、企業努力により様々なおいしい介護食が増えています。食材料費を見ながら、行事食の日だけ、等うまく取り入れていくのも良い手かもしれませんね。皆さんの参考になれば幸いです。
おせちをソフト食にしてみませんか?あの林兼産業様とのコラボ企画!(いろんな商品の試食もできちゃう!?)
現地交流会ソフト食おせちはこちらから!参加無料です♪
栄養士・管理栄養士の転職はDietitianJob!
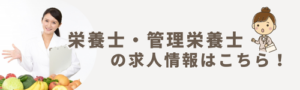
DietitianJob(ダイエッティシャン ジョブ)では、栄養士・管理栄養士の様々な求人を掲載しています。
あなたにあった働き方を一緒に探しませんか?弊社のエージェントは全員実務経験ありの栄養士・管理栄養士!
詳しいお仕事の話や、専門性のある質問にもお答えできるので転職後も安心!
弊社では、あなたの経験や強みを最大限に活かせるようにフォローし、理想の職場への転職をお手伝いします。
詳しくはこちらをご覧ください。
📌 関連記事<シリーズ全10回>










