
<最終更新日 2025.9.18>
高齢者施設施設は管理栄養士の活躍の場として代表的ですね。
老人ホームでの管理栄養士の仕事とは?奮闘記シリーズとして現場でのリアルな様子をお伝えいたします。
👉 目次
管理栄養士が高齢者福祉施設で担う仕事
こんにちは、管理栄養士の廣江です。DietitianJobの運営メンバーになる以前は、特別養護老人ホームで12年勤務していました。
高齢者福祉施設での食事は非常に重要です。病院は「治すため」栄養がしっかり調整された食事が重要であるように、高齢者福祉施設では「楽しんでもらうため」「ご利用者の笑顔のため」として食事が位置付けられています。栄養管理ももちろん大切な事ですが、これがご利用者にとって最後の食事になるかもしれない…そう思うと毎日「ああ今日も美味しかった」そう感じていただけるような食事を出したい、それを胸にに日々取り組んでいました。
管理栄養士の主な業務内容
高齢者福祉施設では栄養管理、給食管理、栄養マネジメント計画等の加算・介護報酬への対応がメインになってきます。施設によっては家族への対応や外部への対応等を行う場合もあります。
ご利用者の栄養管理
まずご利用者の栄養状態の把握です。ご高齢の方は何かしらの病歴や既往をお持ちの方がほとんどです。今現在の健康状態、何が必要なのか、何を制限しないといけないのか、どのくらい日常的に食べているのかを把握するのは最も大切な事です。管理栄養士一人では把握することはほぼ不可能なため、ナースやケアワーカー、ケアマネージャーとの情報交換は欠かせません。
また、正しい食事を提供しても食べきれない、消化吸収率の衰えにより食べても太らない、嚥下状態が落ちカロリーが摂れない、口腔内の状況や運動不足、寝たきり、認知の低下…等々、様々な問題があります。その方にとって無理のない、楽しんでいただける食事内容であるかどうか。無理に食べてもらうのではなく、日々穏やかに過ごしてもらえるように……高齢になるとからだの調子は日々変化していくため、定期的な見直しは絶対に必要となります。
献立の作成、給食管理
委託給食会社が入っている、直営での管理をしている、栄養士が配置されているなど施設にもよりますが、献立作成と発注、食材管理は、管理栄養士にとって非常に重要な業務の一環です。
地域柄やご利用者の年代等により嗜好も変わってくるため、嗜好調査やミールラウンド等で喫食率を把握し、献立に反映するのも大切な仕事です。いくら栄養バランスの取れた献立であっても食べてもらえなければ意味がないのです。高齢者は一度食事を抜いただけで健康を崩してしまうこともしばしばあります。
📌関連記事
喫食調査の実施と本来の調査目的について
また、昨今の食材高騰に合わせ、食材や取引業者の選定等を行う場合もあります。米不足の際にはなかなか見つからず、とても苦労しました。
食事形態の調整
高齢者には、咀嚼や嚥下に難しさを感じる方が多く、介護付きの施設であれば通常食よりも食形態を変更した方のほうが多い場合があります。私が実際に働いていた施設は200食程度出したうち常食は2~30食ほどでした。
噛み切るのが難しい方へは一口大刻み食
より難しい方へはソフト食や極刻み食
嚥下が困難な方へはミキサー食、ゼリー食等
多岐にわたる為調理を行う調理担当にも理解をしてもらうことが大切です。均一に仕上げるべきか、多少粒が不ぞろいでもよいのか。なぜここまで形態調整が必要なのか――調理師等に理解してもらうことが大切です。ご利用者が安心して食事を楽しめる環境を整えることは、管理栄養士の責任であり、やりがいのある仕事といえるでしょう。
※極刻み食、刻み食は嚥下困難者に危険と昨今言われますが、実体験としては必要だと感じています。ソフト食では食べた気にならない、食べたくない、こんなものは食事ではない…これは実際にご利用者から言われた言葉です。いくら正しい栄養配分でも食べてもらえなければ意味がないのです。嚥下状態はもちろん、ご利用者の認知度にあったものを提供するのが管理栄養士としての仕事です。刻んだ際に口腔内でばらけないように薄めのとろみでまとめる、煮物の汁やソースにとろみをつけるなどの工夫をして誤嚥のリスクを減らしていました。
介護報酬、加算の為の記録と整理
主には栄養マネジメント強化加算になってくると思います。
施設により退所時栄養情報連携加算や再入所時栄養連携加算になります。
また、経口移行加算、経口維持加算、療養食加算、リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の一体的取り組み等の加算があります。令和6年の介護報酬改定は高齢者福祉施設において栄養管理の重要性がかなりみられるようになってきたと感じます。これらの加算を算定できるように日々記録を正しく行うのは重要な業務です。
高齢者福祉施設でのノロウイルス
体力の低下している高齢者にとってノロウイルスは非常に脅威になります。健康な成人でさえ数日はまともに食事はおろか水分が摂れないのに、高齢者が罹ると命の危険になりうるのは明白です。
まずは持ち込まない、広めない。ノロウイルスの正しい知識を改めて振り返りましょう。
ノロウイルスとは
ノロウイルスとは、ウイルス性胃腸炎を引き起こす原因の一つで、特に冬季に流行しやすい特性があります。ノロウイルスは非常に感染力が強く、わずかな量でも感染を引き起こすことができます。
感染経路は主に経口で、食事や水、感染者との接触、便や嘔吐物を通じて広がることが多いのは有名ですね。
ノロウイルスに感染すると、主に嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状が現れます。特に嘔吐が激しい場合が多く、感染者は数日にわたり吐き気を催すことがあります。吐瀉物は想像よりも広範囲にわたるため(※1mの高さから落下した場合、地面には半径2m程度に飛散すると言われています)、食堂やトイレ等での嘔吐があった場合、集団生活である施設では他の利用者へ感染が広がることがかなり多いです。
また、ノロウイルスの感染は、一度回復しても体内にウイルスが残る場合があり、感染拡大を防ぐためには感染者が回復した後も注意が必要です。このような症状や影響を理解し、迅速な対応を取ることが、高齢者福祉施設での感染予防につながります。
高齢者福祉施設の栄養士の一般的なノロウイルス対策
調理に携さわる職員の健康管理
ノロウイルスに感染している人が調理に携わると施設内全体への感染拡大につながります。
不顕性感染の可能性を考えると、ノロウイルスの流行シーズンである冬季はノロウイルスのチェックが可能は検便検査を行うことも視野に入れて良いでしょう。
また、大量給食調理マニュアルには調理員専用のお手洗いを用意することが推奨されています。特に勤務中は外部の方も使用可能なお手洗い等を使うのは控えた方が良いでしょう。
加熱での消毒、次亜塩素酸での消毒
ノロウイルスは中心温度85℃~90℃で90秒間以上の加熱で感染力を失います。
料理はもちろん、使用する調理器具もしっかり殺菌しましょう。食器乾燥機等がない、または使用できないものには次亜塩素酸での消毒も効果があります。
皆が触れる扉のノブは消毒しているご施設も多いと思いますが、温冷配膳車の取っ手、エレベーターや照明のスイッチなどは見落としがちです。
次亜塩素酸で消毒する際は濃度0.1~2%で調整し、密室などで使わないようにしましょう。(次亜塩素酸中毒やアルコール等と混ぜるのは危険です。)
ウイルスを持ち込まない
本人の体調不良時はどんなに忙しくてもご利用者の安全が第一のため、休むこと。(出勤しないこと)
家族にノロウイルスがいる場合も同様です。まあこの程度なら…会っていないし大丈夫…その甘さがご利用者の命の危険につながるかもしれない、という自覚を持っていただく事が大事です。
また、急に人が休んだ場合の対応をあらかじめ決めておくのも大切です。自分が勤めていた施設ではコロナ流行時に職員が急に休んだらどうするかの対応をまとめていました。
食器をディスポにし洗浄業務を減らすことや、漬物の提供を中止すること、非常食として取ってあるペースト食等を使用する(ローリングストックとして日常使いへ変更し使い慣れる)等を行っていました。
また、ディスポはご利用者で下痢嘔吐発生時にも使用していました。食器を厨房へ戻さなくてよいので万一ノロウイルスであった場合も安全だったためです。
ノロウイルスではない下痢嘔吐だろうということも多々ありましたが、念のため検査が終わり陰性が確認できるまでは体調不良のご利用者には使い捨て食器を使用しフロアで処分を徹底していました。
少しでも変だな?と感じたら
高齢者はご自分の体調の変化に鈍いこともあります。
普段すごくお話好きな方が話さない、活気がない、ご飯を食べない等少しでもおかしい点があったら他職種と連携しましょう。
また、嘔吐や下痢があった場合は原因が分かるまで隔離や感染対応とするのも有効です。
ここからは有料老人ホームでの奮闘記になります。
今回はノロウイルスが実際に蔓延してしまった際の貴重な経験談です。
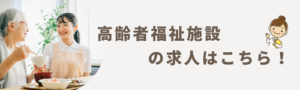
有料老人ホームでの経験談
こんにちは。外部執筆スタッフの管理栄養士 長谷川晴美です。
管理栄養士奮闘記と題しまして、有料老人ホームでの経験をお伝えしていきます。
今回はノロウイルス蔓延時の様子と対策についてです。
皆様の何かのお役に立てれば、嬉しいです。
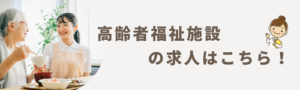
ノロウイルス蔓延時の様子
<2021年に執筆いただいておりますので内容が現在と変わっている点もあります>
有料老人ホームに勤務中の14年間に、保健所に届ける規模のノロウイルス蔓延が二回ありました。
昔むかしは生牡蠣さえ出さなければ避けられるものという認識で、その後は胃腸炎の風邪の一種くらいに思っていましたので、「こんなに蔓延するとは?!」と衝撃的でした。
最初の蔓延は、クリスマスシーズン頃からぽつりぽつりと下痢嘔吐の症状の入居者が出始め、そのうちに職員も増えていき、とにかく毎日毎日、また?!また?!また?!という感じで症状のある方がどんどん増えていきました。
・下痢嘔吐のある方への食事内容の変更や使い捨て食器の手配
・食堂担当者や配膳担当者や厨房スタッフへの細かな指示
・職員や他入居者への注意喚起、感染症対策緊急会議等
イレギュラーな仕事が増え、休むわけにもいかず、休んでいる職員も増え人手も足りず、さすがの私もかなり疲労困憊でした。
自分自身も症状が出ていないだけで感染しているのではないか、いつ感染するかなどの不安もありながらの勤務でしたが、私自身は二度とも何事もなく乗り越えました。
厚生労働省の高齢者介護施設における感染対策マニュアルに従い、保健所に届け出を出し終息するまでの約2か月間、保健所へ感染状況を毎日報告しました。
📌参考 介護現場における感染対策の手引き
1回目の蔓延は、症状の出方から集団食中毒ではないとの見解で現地調査はなしでした。
1回目の蔓延から数年後の2回目の蔓延は、同じ時期くらいに発生し、その時は2回目ということもあり保健所の現地調査が入りました。
「集団食中毒だったら、やることはやって責任をとって辞表を出そう」と腹をくくっている状況でしたが、こちらも集団食中毒ではないという見解でした。
どのように蔓延したかは明確ではありませんが、1回目の蔓延時は、外食で生牡蠣を食べて下痢症状がある入居者が、大浴場を使用していたこと、嘔吐物処理をした職員がきちんと処理せず蔓延させてしまったことが考えられました。
2回目の蔓延時は、1度目の経験から予防対策をしっかりしていたので感染経路不明で、「これだけやっていたのに」と落胆したのを今でも覚えています。
保健所とのやりとり
保健所に報告が必要な場合
ア 同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死亡者や 重篤患者が 1 週間以内に 2 名以上発生した場合
イ 同一の感染症や食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が 10 名 以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ 上記以外の場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の 発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
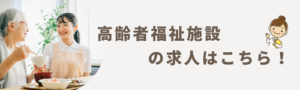
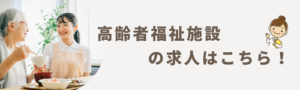
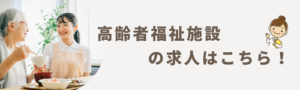
・保健所からの助言と対策
①マニュアルを職員全員に周知徹底。特にノロウイルス対策セットの設置場所の周知。
⇒・職員研修の改善
②ご飯のセルフサービスのしゃもじの共有禁止
⇒・厨房内で盛り付けが一番だが、入居者の自立や自由な選択を考えセルフスタイルの策。
・入居者人数分のしゃもじと使用前と使用済のしゃもじ入れを用意する。
・入居者がしゃもじの使い方に慣れるまでは案内人をつける。
③厨房職員専用トイレ
⇒・休憩部屋についているトイレのみの使用を徹底。
・トイレ専用の履物の設置、トイレ後の専用の手洗い場所の確保。
④ハンドソープや消毒液の継ぎ足し禁止
⇒・担当に指導し実施状況の確認。
・容器を洗って乾燥させるので、必要量の容器を買い足す。
⑤厨房以外で調理したものの提供を控える
⇒・恒例の餅つき大会は無期限の中止。
有料老人ホームにおけるノロウイルス予防対策
感染症予防や発生時に中心となって動く、各部署からの代表委員で構成した感染症対策委員会を設置していました。
情報収集と発信やマニュアル管理、感染症予防を中心に、職員、入居者、面会の家族、外部業者への注意喚起等の活動を主に行っていました。
あとで詳しくお話しますが、例えば、職員には、研修はもちろん、生の二枚貝を食べることを禁止し、いつでも嘔吐者の対応ができるように使い捨てビニール手袋常備を義務付けていました。
入居者へ掲示や呼びかけや予防教室、家族や業者に掲示やプリント配布等をしていました。
また、嘔吐物処理のためのノロウイルス対策セットは各部署と食堂、送迎バスにセットし毎年過不足等の確認をすることも行っていました。
ちなみに、ノロウイルス対策セット内容は、使い捨て手袋、マスク、使い捨て予防衣、ビニール袋、新聞、ペーパータオル、雑巾、次亜塩素酸ナトリウム、水、ペットボトル、スリッパです。
蔓延時は職員全員で毎日全館消毒と換気を行いましたが、蔓延時の翌年からは、12月から2月末まで担当表を作成し職員全員で毎日全館消毒と換気を行うことにしました。
だいたい一人当たり、週1回1時間程度の割り当てになりましたが、どの部署もなんとか時間のやりくりをして継続していきました。
消毒方法は、次亜塩素酸ナトリウムを専用バケツで薄めて、専用タオルで手すりやドアノブ、エレベーターのボタン等の手で触れるものを、換気をしながら消毒してまわりました。
マニュアル作成と見直し
最初は2~3ページ程度のマニュアルも毎年見直し、蔓延後はさらに増えていきました。
保健所の講習会等に参加し情報収集に努め、嘔吐物処理に関しては保健所の資料自体も数回変わったのでその都度変更し、
「ウイルスが飛散するので消毒液の噴霧禁止」「効果がなくなるので消毒液の作り置き禁止」などの情報が入れば、都度追記しました。
嘔吐物処理に関しては、施設独自のアレンジもしました。
というのも、認知症の方がいる、他入居者がいる共用の場所では、嘔吐物に消毒液をかけて放置することは実際的ではなかったからです。
使い捨て手袋を二重にして、放置なしで処理をする方法も記載しました。
蔓延後、入居者からは、隔離期間の不満や、使い捨て食器の不満、見舞いができないことの不満など、たくさんのご意見をいただきました。
そのこともふまえ、最初の蔓延時は一週間の隔離期間でしたが、症状がおさまって48時間の隔離期間にかえ、共用の大浴場やトイレは使用禁止にさせていただくなどの対策をとりました。
使い捨て食器使用は必須ではなく、蔓延の規模に応じて緊急会議で使う時期を話し合うことにも変えました。
その分、食器の消毒方法、残菜処理方法、厨房への受け渡し方など事細かにマニュアル化しました。
ノロウイルス対策セットは各部署と食堂にセットしたものの、使いっぱなしの事態もあり、使った場合の補充の仕方や担当まで決め、マニュアルにも記載しました。
やればやるほど問題がでてくるので、その都度話し合い、マニュアル変更という流れで、終わりなき作業でした。
入居者対象感染症予防教室と職員研修
感染症対策委員会が中心となり、入居者対象感染症予防教室を毎年開催し、基本的な知識や手洗いと手指消毒の仕方、風邪症状がある場合の報告のお願いなどをお伝えし、別に手洗い週間を設け食堂の手洗い場で呼びかけ等を行いました。
職員研修では、全体研修で基本的知識はもちろん、ノロウイルス対策セットの設置場所の確認、嘔吐物処理の実践をします。
応用編として、入居者が食堂で嘔吐された場合を想定し、感染症対策委員が入居者役になり、その場で指名された職員が対応し、それを見ながら全員で意見を出しあい問題点等をだしていく、自ら考えて行動できるような研修スタイルにもしました。
例えば、「車椅子が原因で広がるよね」、「通った道も消毒した方がいいね」「他の入居者を他の席に誘導するから食堂が職員一人では対応できなくなるよね」などなど、意見も活発にでました。
全体研修後は、再度各部署研修で嘔吐物処理の手順の唱和をする期間や、部署ごとに再度嘔吐物処理実践を行いました。
3度目はないようにと願いながら・・・
次回は、非常食についてお伝えする予定です。
📌老人ホームで働く管理栄養士の奮闘記 ~ 防災 非常食 ~
まとめ
ノロウイルスの蔓延は、有料老人ホームで管理栄養士として働く私にとって、想像以上の試練であらゆる手を打たねばなりませんでした。毎日の報告、全館消毒、手洗い・手指消毒の徹底などは、疲労を伴いながらも「安全を守る」という責任の重さを痛感する経験でもありました。こうした対応策のひとつひとつが、入居者の安心と施設の信頼につながるのだと改めて感じます。みなさんもこの体験から、いざという時の備えの大切さを感じ取ってもらえたら嬉しいです。
栄養士・管理栄養士の転職はDietitianJob!
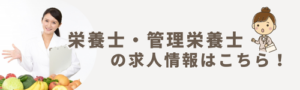
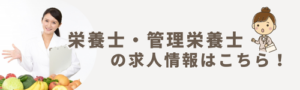
DietitianJob(ダイエッティシャン ジョブ)では、栄養士・管理栄養士の様々な求人を掲載しています。
あなたにあった働き方を一緒に探しませんか?弊社のエージェントは全員実務経験ありの栄養士・管理栄養士!
詳しいお仕事の話や、専門性のある質問にもお答えできるので転職後も安心!
弊社では、あなたの経験や強みを最大限に活かせるようにフォローし、理想の職場への転職をお手伝いします。
詳しくはこちらをご覧ください。
📌 関連記事<シリーズ全10回>







