
<最終更新日 2025.9.18>
高齢者施設施設は管理栄養士の活躍の場として代表的ですね。
老人ホームでの管理栄養士の仕事とは?奮闘記シリーズとして現場でのリアルな様子をお伝えいたします。
👉 目次
管理栄養士が高齢者福祉施設で担う仕事
こんにちは、管理栄養士の廣江です。DietitianJobの運営メンバーになる以前は、特別養護老人ホームで12年勤務していました。
高齢者福祉施設での食事は非常に重要です。病院は「治すため」栄養がしっかり調整された食事が重要であるように、高齢者福祉施設では「楽しんでもらうため」「ご利用者の笑顔のため」として食事が位置付けられています。栄養管理ももちろん大切な事ですが、これがご利用者にとって最後の食事になるかもしれない…そう思うと毎日「ああ今日も美味しかった」そう感じていただけるような食事を出したい、それを胸にに日々取り組んでいました。
管理栄養士の主な業務内容
高齢者福祉施設では栄養管理、給食管理、栄養マネジメント計画等の加算・介護報酬への対応がメインになってきます。施設によっては家族への対応や外部への対応等を行う場合もあります。
ご利用者の栄養管理
まずご利用者の栄養状態の把握です。ご高齢の方は何かしらの病歴や既往をお持ちの方がほとんどです。今現在の健康状態、何が必要なのか、何を制限しないといけないのか、どのくらい日常的に食べているのかを把握するのは最も大切な事です。管理栄養士一人では把握することはほぼ不可能なため、ナースやケアワーカー、ケアマネージャーとの情報交換は欠かせません。
また、正しい食事を提供しても食べきれない、消化吸収率の衰えにより食べても太らない、嚥下状態が落ちカロリーが摂れない、口腔内の状況や運動不足、寝たきり、認知の低下…等々、様々な問題があります。その方にとって無理のない、楽しんでいただける食事内容であるかどうか。無理に食べてもらうのではなく、日々穏やかに過ごしてもらえるように……高齢になるとからだの調子は日々変化していくため、定期的な見直しは絶対に必要となります。
献立の作成、給食管理
委託給食会社が入っている、直営での管理をしている、栄養士が配置されているなど施設にもよりますが、献立作成と発注、食材管理は、管理栄養士にとって非常に重要な業務の一環です。
地域柄やご利用者の年代等により嗜好も変わってくるため、嗜好調査やミールラウンド等で喫食率を把握し、献立に反映するのも大切な仕事です。いくら栄養バランスの取れた献立であっても食べてもらえなければ意味がないのです。高齢者は一度食事を抜いただけで健康を崩してしまうこともしばしばあります。
📌関連記事
喫食調査の実施と本来の調査目的について
また、昨今の食材高騰に合わせ、食材や取引業者の選定等を行う場合もあります。米不足の際にはなかなか見つからず、とても苦労しました。
食事形態の調整
高齢者には、咀嚼や嚥下に難しさを感じる方が多く、介護付きの施設であれば通常食よりも食形態を変更した方のほうが多い場合があります。私が実際に働いていた施設は200食程度出したうち常食は2~30食ほどでした。
噛み切るのが難しい方へは一口大刻み食
より難しい方へはソフト食や極刻み食
嚥下が困難な方へはミキサー食、ゼリー食等
多岐にわたる為調理を行う調理担当にも理解をしてもらうことが大切です。均一に仕上げるべきか、多少粒が不ぞろいでもよいのか。なぜここまで形態調整が必要なのか――調理師等に理解してもらうことが大切です。ご利用者が安心して食事を楽しめる環境を整えることは、管理栄養士の責任であり、やりがいのある仕事といえるでしょう。
※極刻み食、刻み食は嚥下困難者に危険と昨今言われますが、実体験としては必要だと感じています。ソフト食では食べた気にならない、食べたくない、こんなものは食事ではない…これは実際にご利用者から言われた言葉です。いくら正しい栄養配分でも食べてもらえなければ意味がないのです。嚥下状態はもちろん、ご利用者の認知度にあったものを提供するのが管理栄養士としての仕事です。刻んだ際に口腔内でばらけないように薄めのとろみでまとめる、煮物の汁やソースにとろみをつけるなどの工夫をして誤嚥のリスクを減らしていました。
介護報酬、加算の為の記録と整理
主には栄養マネジメント強化加算になってくると思います。
施設により退所時栄養情報連携加算や再入所時栄養連携加算になります。
また、経口移行加算、経口維持加算、療養食加算、リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の一体的取り組み等の加算があります。令和6年の介護報酬改定は高齢者福祉施設において栄養管理の重要性がかなりみられるようになってきたと感じます。これらの加算を算定できるように日々記録を正しく行うのは重要な業務です。
高齢者福祉施設の非常食
東日本大震災までは3日間と言われていましたが、3日経っても救援物資が届かなかった地域があった、という現実があり、非常時には本当に何があるか分からないものです。
私が以前働いていた施設では理事長の意向で5日間の準備+αをしていました。また、施設によっては広域避難場所・福祉避難所に指定されているところもあるでしょう。その場合は自施設だけではなく自治体から配布される非常食の管理を行う必要があります。
非常食選びのポイント
通常の非常食では
*食べなれているものであるか
*栄養バランスやカロリーは取れているか
*保存が効くのか
があげられると思いますが、それに加えて高齢者福祉施設の非常食選びのポイントは
*食事形態に合っているか
*調理員が万一いなくても用意できるか
*集団になるので衛生管理ができるか
も必要となってきます。人数の多い施設では缶詰ももちろん良いですが、フリーズドライ等の方が重みがなくて良いかもしれません。
非常食のパンやご飯は、意外と食べてみると固く適さないものが多いです。防災の日や311の際にローリングストックとし提供した際に、本当に適した非常食なのか確認するのは非常に重要です。羊羹などもすすめられていますが嚥下困難な方が食べれるものなのか、必ず管理栄養士本人が試食し判断をするのが非常時の安全につながります。
私が勤務していた特別養護老人ホームでは、刻み食等の嚥下困難な方に適したものがなかなか見つからず、賞味期限が1年程度のレトルトパウチや高栄養のゼリー飲料、おかずカップゼリーを少しずつ使いローリングストックして非常食としていました。また、電気が通らないとミキサー等も使えません、ミキサー食用のお粥パウダー(お湯に溶かすだけで均一なミキサー粥ができる)等、現在は良い商品が出ています。日ごろから使い慣れておくのも良いでしょう。
献立以外でも用意した方が良い食品
水分がとろみまたはゼリーのご利用者が少なからずいる場合は水分補給兼用のゼリー類はあるに越したことはありません。カセットコンロがあっても毎食ゼリーを調理するのは難しいと思います。(人数にも寄りますが)
水分補給ゼリーは発熱時に提供しローリングストックをしていました。使い慣れていることは職員たちの平常心を取り戻すのに役に立つことでしょう。
ここからは有料老人ホームでの奮闘記になります。
今回は有料老人ホームでの実際に支度していた非常食のお話です。
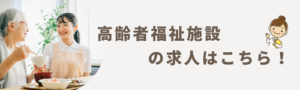
有料老人ホームでの経験談
こんにちは。外部執筆スタッフの管理栄養士 長谷川晴美です。
管理栄養士奮闘記と題しまして、有料老人ホームでの経験をお伝えしていきます。
今回は 防災・非常食についてです。
皆様の何かのお役に立てれば、嬉しいです。
⇒防災食のお話、皆さんでしませんか?8月2日開催!
(終了いたしました。クリックすると報告ブログが読めます)
 最新の防災食についてや施設の防災食について等♪
最新の防災食についてや施設の防災食について等♪
介護施設における非常食の考え方
非常食は3食3日9回分、常食と介護食、入居者と職員分を準備していました。
夜間帯に災害が発生した場合に入れ歯をしていないことも想定し、介護食は必要人数よりも多めにしていました。
最初の3回は火を使わなくても食べられるものとして、そのまま配って飲食できるお粥のレトルトパックやパンの缶詰、お茶缶等にし、介護食は9回分すべてそのまま食べられる商品にしていました。
おかずは、普段提供している献立でアレンジして使えるような魚や肉の缶詰を選び、期限前に献立に入れて使用するようにし、できるだけ廃棄がないように考えていました。
東日本大震災後は、工場が被災し魚缶詰の入荷ができなく、メニューを変えた期間もありました。
その他の備品として、1箱50人前のご飯を作るのにお湯が必要なので(水でも作れます)、5年保存の水、カセットコンロやカセットボンベ、お祭りに使用しているコンロやLPガス、やかんや使い捨て食器類も、防災倉庫に置いていました。
必要な水の量やガスの量は、間違えがないようしっかり計算しつつ多めに準備し、防災倉庫は、設置場所の地盤が弱いところだったので移動をしたり新しくするなど、できる備えをしていきました。

防災意識を高めるために
東日本大震災よりかなり前の時期に、夜中に震度5以上の地震があり、「とうとう来たかー」と恐怖を感じるくらいの大きな地震がありました。
自宅で寝ていた私は、とっさに娘たちをかばいながらおさまるのを待ち、おさまって一安心したところで、職場が心配になり電話をしました。
電話に出た夜警さんからは、被害はないようだとのことで、「何かあったら行くので電話をください」とお伝えして電話を切りました。
翌日、出勤をしたときに夜警さんから聞かされたのは、職場に心配の電話をしたのが、私と介護課長のみだったらしく、理事長が落胆していたという話でした。
その後、「地震時はどんな行動をして何を思ったか」などのアンケートが配られ、これを期に、経営者側は職員の意識改革に力を入れていきました。
のちに防災委員会が立ち上がり、様々な活動が活発に行われていきました。
有料老人ホーム協会主催の事例研究発表会というものが年1回行われていました。
テーマは、認知症対応や苦情対応、食事やリハビリ、防災など様々です。
施設長が元自衛隊員で、避難訓練の厳しさに職員みんなが悲鳴をあげているという、ちょっとクスッと笑える話もありましたが、私が参加させていただいた年度は、東日本大震災の後でしたので、福島県の施設での生々しい体験談を聞くことができ、胸がつまる思いになったのを今でも覚えています。
他人事ではないことを再認識し、直接体験談を聞くことにまさるものはないと感じました。
防災委員会との連携
防災委員会が設置され、様々な想定をした避難訓練や必要と思われる設備などが徐々に整えられていきました。
私自身も、非常食メニューや防災倉庫の鍵の場所の周知徹底等を知ってもらうために、希望して防災委員会に入れてもらいました。
東日本大震災後は、「非常食は5~7日分あった方が望ましい」「温かい物や甘い物が嬉しかった」との情報が防災委員会から入り、厨房の材料で3~4日分の材料と甘い物も常にあることを確認し、防災倉庫の備蓄は今まで通りの3日分でいいことにしました。

期限が切れるものを利用し、職員や入居者対象の非常食講習会や各部署で炊き出しの練習などもしてもらいました。
入居者と職員に、缶詰等を配っている最中に、1ケースだけ期限が切れているものがあることに気づいて、あわてて回収したという失敗もありました。
うっかり期限を切らせてしまったときには、注文し納品されるまでの間は、「どうか災害がおきませんように・・・」と願いつつ、配れないものを開けて中身を捨てる作業も、かなりの一仕事でした。
以上のような失敗がないよう、その後は私だけでなく、二重チェックで防災委員にもチェックしてもらうシステムにしました。
私たち栄養士も施設の一員として、想定外がないよう危機管理能力を最大限に発揮し、できる準備をしっかりしておきたいですね。
しかしながら、災害が起きないことを切に願います!
次回は、栄養ケアについてお伝えする予定です。
📌老人ホームで働く管理栄養士の奮闘記 ~栄養ケアマネジメント~
まとめ
非常食や防災準備は、「いざというとき」の安心に直結する管理栄養士の重要な仕事。長谷川さんの体験からは、3日分の非常食を常備し、職員・利用者を含めた介護食メニューも想定外を考慮して余裕を持たせること、防災倉庫の備品管理や避難訓練、委員会での意識共有など、「備え」を日常の一部とする工夫が感じられます。失敗や期限切れといったリアルな経験から学び、二重チェック体制を敷いたことも印象的。読んでいて、自分の施設でも防災体制を見直したほうがいいかもしれない、と思わせられますね。皆さんの参考になれば幸いです。
栄養士・管理栄養士の転職はDietitianJob!
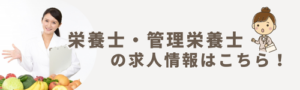
DietitianJob(ダイエッティシャン ジョブ)では、栄養士・管理栄養士の様々な求人を掲載しています。
あなたにあった働き方を一緒に探しませんか?弊社のエージェントは全員実務経験ありの栄養士・管理栄養士!
詳しいお仕事の話や、専門性のある質問にもお答えできるので転職後も安心!
弊社では、あなたの経験や強みを最大限に活かせるようにフォローし、理想の職場への転職をお手伝いします。
詳しくはこちらをご覧ください。
📌 関連記事<シリーズ全10回>









