
<最終更新日 2025.9.18>
高齢者施設施設は管理栄養士の活躍の場として代表的ですね。
老人ホームでの管理栄養士の仕事とは?奮闘記シリーズとして現場でのリアルな様子をお伝えいたします。
📌 関連記事<シリーズ全10回>
- 第1回 老人ホームで働く管理栄養士の奮闘記 ~仕事内容と献立作成~
- 第2回 老人ホームで働く管理栄養士の奮闘記 ~介護食~
- 第3回 老人ホームで働く管理栄養士の奮闘記 ~ノロウイルスの対応と対策~
- 第4回 老人ホームで働く管理栄養士の奮闘記 ~ 防災 非常食 ~
- 第5回 老人ホームで働く管理栄養士の奮闘記 ~栄養ケアマネジメント~
- 第6回 老人ホームで働く管理栄養士の奮闘記 ~接遇マナー~
- 第7回 老人ホームで働く管理栄養士の奮闘記 ~苦情対応とメンタルケア~
- 第8回 老人ホームで働く管理栄養士の奮闘記 ~介護予防とレクリエーション~
- 第9回 老人ホームで働く管理栄養士の奮闘記 ~行事・行事食~
- 第10回 老人ホームで働く管理栄養士の奮闘記 ~異物混入~
<最終更新日 2025.9.18>
👉 目次
管理栄養士が高齢者福祉施設で担う仕事
こんにちは、管理栄養士の廣江です。DietitianJobの運営メンバーになる以前は、特別養護老人ホームで12年勤務していました。
高齢者福祉施設での食事は非常に重要です。病院は「治すため」栄養がしっかり調整された食事が重要であるように、高齢者福祉施設では「楽しんでもらうため」「ご利用者の笑顔のため」として食事が位置付けられています。栄養管理ももちろん大切な事ですが、これがご利用者にとって最後の食事になるかもしれない…そう思うと毎日「ああ今日も美味しかった」そう感じていただけるような食事を出したい、それを胸に日々取り組んでいました。
管理栄養士の主な業務内容
高齢者福祉施設では栄養管理、給食管理、栄養マネジメント計画等の加算・介護報酬への対応がメインになってきます。施設によっては家族への対応や外部への対応等を行う場合もあります。
ご利用者の栄養管理
まずご利用者の栄養状態の把握です。ご高齢の方は何かしらの病歴や既往をお持ちの方がほとんどです。今現在の健康状態、何が必要なのか、何を制限しないといけないのか、どのくらい日常的に食べているのかを把握するのは最も大切な事です。管理栄養士一人では把握することはほぼ不可能なため、ナースやケアワーカー、ケアマネージャーとの情報交換は欠かせません。
また、正しい食事を提供しても食べきれない、消化吸収率の衰えにより食べても太らない、嚥下状態が落ちカロリーが摂れない、口腔内の状況や運動不足、寝たきり、認知の低下…等々、様々な問題があります。その方にとって無理のない、楽しんでいただける食事内容であるかどうか。無理に食べてもらうのではなく、日々穏やかに過ごしてもらえるように……高齢になるとからだの調子は日々変化していくため、定期的な見直しは絶対に必要となります。
献立の作成、給食管理
委託給食会社が入っている、直営での管理をしている、栄養士が配置されているなど施設にもよりますが、献立作成と発注、食材管理は、管理栄養士にとって非常に重要な業務の一環です。
地域柄やご利用者の年代等により嗜好も変わってくるため、嗜好調査やミールラウンド等で喫食率を把握し、献立に反映するのも大切な仕事です。いくら栄養バランスの取れた献立であっても食べてもらえなければ意味がないのです。高齢者は一度食事を抜いただけで健康を崩してしまうこともしばしばあります。
📌関連記事
喫食調査の実施と本来の調査目的について
また、昨今の食材高騰に合わせ、食材や取引業者の選定等を行う場合もあります。米不足の際にはなかなか見つからず、とても苦労しました。
食事形態の調整
高齢者には、咀嚼や嚥下に難しさを感じる方が多く、介護付きの施設であれば通常食よりも食形態を変更した方のほうが多い場合があります。私が実際に働いていた施設は200食程度出したうち常食は2~30食ほどでした。
噛み切るのが難しい方へは一口大刻み食
より難しい方へはソフト食や極刻み食
嚥下が困難な方へはミキサー食、ゼリー食等
多岐にわたる為調理を行う調理担当にも理解をしてもらうことが大切です。均一に仕上げるべきか、多少粒が不ぞろいでもよいのか。なぜここまで形態調整が必要なのか――調理師等に理解してもらうことが大切です。ご利用者が安心して食事を楽しめる環境を整えることは、管理栄養士の責任であり、やりがいのある仕事といえるでしょう。
※極刻み食、刻み食は嚥下困難者に危険と昨今言われますが、実体験としては必要だと感じています。ソフト食では食べた気にならない、食べたくない、こんなものは食事ではない…これは実際にご利用者から言われた言葉です。いくら正しい栄養配分でも食べてもらえなければ意味がないのです。嚥下状態はもちろん、ご利用者の認知度にあったものを提供するのが管理栄養士としての仕事です。刻んだ際に口腔内でばらけないように薄めのとろみでまとめる、煮物の汁やソースにとろみをつけるなどの工夫をして誤嚥のリスクを減らしていました。
介護報酬、加算の為の記録と整理
主には栄養マネジメント強化加算になってくると思います。
施設により退所時栄養情報連携加算や再入所時栄養連携加算になります。
また、経口移行加算、経口維持加算、療養食加算、リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の一体的取り組み等の加算があります。令和6年の介護報酬改定は高齢者福祉施設において栄養管理の重要性がかなりみられるようになってきたと感じます。これらの加算を算定できるように日々記録を正しく行うのは重要な業務です。
ここからは有料老人ホームでの奮闘記になります。
今回は有料老人ホームでの苦情対応のお話です。
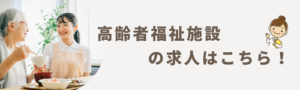
有料老人ホームでの経験談
こんにちは。外部執筆スタッフの管理栄養士 長谷川晴美です。
管理栄養士奮闘記と題しまして、有料老人ホームでの経験をお伝えしていきます。
今回は 苦情対応とメンタルケアについてです。
皆様の何かのお役に立てれば、嬉しいです。
有料老人ホームにおける苦情対応
有料老人ホーム等の介護施設では、苦情を受け付けるための窓口を設置するという法律上の義務があります。
この苦情相談窓口は、
・施設内で苦情対応責任者を選任する
・県や市などの「苦情窓口の連絡先」などを明記して、入居前にお渡しする重要事項説明書等で入居者やご家族に説明する
・施設内の掲示板などの公共の場にも「苦情窓口の連絡先」を掲示
することが必要です。
施設外まで、苦情をうったえなければならないほど、追い詰めてしまわないように、施設内でしっかり体制を整えて取り組まなければなりません。
入居者やそのご家族が、気持ちよく安心した日々を過ごしいただくためには、接遇マナーとあわせて苦情対応も重要になります。
苦情は、欲求が満たされなかった時に、不満や不安が溜まってしまい、苦情を訴えたという流れがほとんどです。
介護施設は、直接ふれあう機会が多い職種ですので、苦情ゼロはなかなか難しいですが、どのようなご意見も真摯に受けとめ、対策を考え迅速に動くことが、大きな苦情へつながることを防ぎます。
相手を軽んじた言葉や態度はもちろんですが、コミュニケーション不足等による考え方やとらえ方の行き違いも苦情につながります。
私が特に苦情につながりやすいと感じたことは、
「あやまらずに言い訳から入る」
「対応や報告が遅い」
「個人の判断だけで動く」
「傾聴の姿勢や改善の傾向がみられない」ことです。
苦情では、お詫びの言葉を求めることが多いですが、内容によっては、共感、気持ちに寄り添うニュアンスのクッション言葉「気付けずに申し訳ございません。ご意見ありがとうございます。」という言葉を添えるのも有効です。
そして、口だけにならないように、お詫びをしたあとは、改善に向けて迅速に動くことです。
どうにもならないような苦情もありますが、「はっと気づかされるもの」や「サービス改善のてがかり」になる内容も多々あり、声を上げてくれるのはありがたいことでもあります。

苦情を減らすための取り組み
苦情を減らすには、苦情になる前段階のご意見を吸い上げやすい体制作りです。
ご意見箱の設置やアンケート調査は有効です。
ただし、誰がどのように管理するかまで決めておかないと、聞きっぱなしの状態になってしまい、逆効果になってしまうので要注意です。
その他、入居者と職員(各部署長等)の話し合い、入居者の家族と職員の話し合いも定期的に開催していました。
個別対応として、相性のいい職員が、定期的にお部屋まで傾聴にうかがうケアプランもあり、その時間をもうけることによって、忙しい業務の中で気づきづらいことに向かい合うことができます。
ご意見のうちに対応をしておくことがひとつのポイントです。
苦情は、アドバイスやご意見という意味合いも多いですが、気持ちをわかってほしい、改善してほしいという要求につながっています。
相手の訴え方は、いろいろあると思いますが、奥にある気持ちを推しはかって把握していくのが第一歩です。
ここでは接遇マナーと経験がものを言います。
相手の立場で、共感しつつ、できる限り要望に応える姿勢を示します。
相手が興奮して苦情を言っているときには、暴言や支離滅裂ないろいろな話がでてくることもあるでしょう。
接遇やマナーとしての基本は、相手が話しているときに話を折らないことですが、理不尽な訴えを一方的にされていたり、相手が完全に誤解していたり、人格否定的な発言をされると物を申したくなります。しかし、ここはぐっとこらえます。
苦情対応のときには、ポイントを押さえて対応する必要があります。
苦情の対象が自分には無関係なことだとしても、自分が代表で対応しているという気持ちも大切です。
テクニックとしては、相手が興奮しているときは落ち着いて全て聞き、その場では答えなどは出さずに持ち帰るということもひとつです。
または、相手の話について一通り傾聴し、相手の興奮や感情が静まったところで、話の内容を整理していきます。
それに合わせ、自分に答えられる範囲で自分たちの立場、自分たちの事情などを説明して、相手の同意や共感を得られているか確かめていきます。
相手があまりにも一方的な場合は難しいですが、事情を伝えることで理解を示してくださる方もいます。
そして、ビジネスの基本、「報・連・相」は、ここでも重要になります。
報告:内容を上司や先輩等に伝えること
連絡:関係者に発信すること
相談:上司や先輩等からアドバイスをもらうこと
ここでは、失念したり行き違いにならないように、ご意見聞き取り票を作成しました。
食事関係のご意見は一番多いので、管理栄養士の私用は別書式にしました。
苦情対応の実際の流れ
*ご意見と初期対応の内容を記入
⇒部署長に提出
⇒部署長から関係部署に連携
⇒関係部署は対応策を考え対応
⇒対応内容と結果を記入
⇒発信部署にフィードバック
⇒記録としてファイリング
職員の接し方の不満等、部署長やケアマネージャーに直接訴えがあった場合、比較的早く解決できることもありますが、最初の訴えを聞き取った職員の対応の仕方で、大きく方向性がかわります。
「仲間をかばうつもりで報告をしなかった」「重大なことと思わなかった」などで報告がなされない、失念等で他部署との連携がうまくいかなかった、相談しないで自己判断で動いてしまった等が大きな苦情になります。早急に対応したいという気持ちもありますが、それが裏目にでることもあり、すぐに部署長が出て行かない方がいい場合もあります。
ケースバイケースで答えは一つではないですが、過去の事例等を参考に、みんなで向き合うことで、解決策が見いだせます。
あきらめない心で取り組んでいただけたらと思います。

対応後のメンタルケア
入居者のメンタルケアも大切ですが、職員のメンタルケアも大切です。
苦情等は負のエネルギーがありますので、聞くだけでもかなりのパワーを消耗します。
理不尽なことを言われ消化しきれず、やめていく事務員、看護師、介護士もいました。
特に、精神的に堪える事例として、『とられ妄想』*の犯人になってしまうことです。
そのような職員を何人も見てきました。精神誠意をつくしているのに、いわれのないことを言われ、泥棒扱いされることは本当につらいことです。
どういうわけか、志ある人や優しさや真面目さを絵に描いたような人に限ってそのターゲットになったりもします。
*『とられ妄想』とは、物盗られ妄想ともいい、認知症で起きやすい被害妄想で、物を盗まれたと訴える症状で、この犯人が職員個人に限定されることもあります。しまい忘れや記憶違いで、もともとないこともあります。しまい忘れで、見つかったとしても、「犯人がばれないうちに返しにきた」ということにもなり永遠解決しません。財布や現金、通帳や印鑑や貴金属と限らず、下着や冷蔵庫の高級肉が盗まれた、パソコンを勝手に使われているというケースもありました。
このような場合には、上司が定期的にその職員の気持ちを傾聴したり、同じ経験をしたものが声をかけるような体制にしていました。
これは、心配の気持ちがあれば自然にできて当たり前のことですが、とにかく人手が足りず時間に追われる職種ですので、意識しないとできないのが現状です。
トップ2がターゲットになったときは、理事長クラスがフォローしていました。
また、精神的ではなく物理的対策として、部署替えや担当替えなどを行い、接しなくていいような環境にする対策も可能な限り行いました。
もちろん、その職員に説明し納得をしてもらったうえでの異動です。
私の場合は、ひとり管理栄養士で、食事は365日3食、ご意見が出ないはずもなく、その対応に追われている日々でした。
メンタル強めの私ですが、一番堪えた出来事があります。
栄養士に来た苦情
片麻痺のあるご主人が入居し奥様は通い妻というパターンの方でした。
その夫婦の苦情の対象が、最初は看護師、次は介護士、いつか来るだろうと覚悟はしていましたが、最後は私にターゲットがかわっていきました。
食堂の席や食事等が引き金だったのかもしれませんが、「無能な栄養士」など人格否定的な言葉を浴びせられ続けた時期もありましたし、やってもいないことの犯人になったり、こちらが訴えたいくらいでした。
栄養士語録と題して、私の言葉尻を集めて私が読んでも酷い栄養士だと思える仕上がりのノートも突きつけられ、まさしくスキャンダル芸能人の気持ちでした(>_<)
自分のモチベーションが下がらないように、他の入居者の笑顔を見て癒し、過去にお世話になった管理栄養士の先輩に話を聞いてもらって、励ましてもらいつつ、日々を乗り切っていました。その後は、たまたま施設改革で引き抜いた施設長経験者の女性が、うまくクッションになってくれておさまりました。助ける神あり!
その方とは、今では年賀状の付き合い程度ですが、今も感謝しています。
その後ですが、落ち着いて平和になった矢先にストレスからか、突発性難聴、アトピー性皮膚炎の悪化に見舞われ、かなりあせりましたが、割と早くに回復しました。
聞きたくないことを聞かなければならいストレスがあったからか、体の方が正直です。
そんなこともありましたが、「理解してくれる仲間がいる」「一人じゃない」「弱音をはいてもいい」「やることをやって時を待とう」というマインドが身を助けたと感じています。
マインドフルネスストレス低減法
私のおすすめ、マインドフルネスストレス低減法をご紹介します。
マインドフルネスストレス低減法 J.カバットジン (株)北大路書房 (2020年)は教科書のような本ですが2007年に翻訳され、2020年に増版されています。
私は心理学の大学で学びましたが、今は医学やビジネス界、社員研修に取り入れられています。
私たちは、今この瞬間を生きているようでいて、実は過去や未来のことを考えて、「心ここにあらず」の状態が多くの時間を占めています。
特に、過去の失敗や未来の不安といったネガティブなことほど、考えを占める時間が長くなりがちです。
つまり、自分で不安やストレスを増幅させてしまっているのです。
こうした心ここにあらずの状態から抜けだし、心を”今”に向けた状態を「マインドフルネス」といいます。
マインドフルネスとういと難しく特別な印象を受けるかもしれませんが、座禅をイメージしていただけるとわかりやすいかもしれません。
マインドフルネスは、今に意識を集中するので過去や未来の心配事から離れられ、それによって、ストレスをたまりにくくしたり、脳を活性化させ仕事のパフォーマンスを上げる効果があります。
ぼーっとしようと思ってもリラックスしようと思っても意外と難しいですが、呼吸を意識することで、結果的には今に集中することができます。
つきつめようとすると奥が深いですが、練習をすれば簡単にでき、そして効果があります。
心を“今”に向けたマインドフルネスの状態に到達する手段として、マインドフルネスストレス低減法の基本を抜粋しました。
マインドフルネスストレス低減法
基本となる呼吸のトレーニング
あおむけで寝るか、あるいは椅子に座るか、どちらか楽な姿勢を選んでください。
座る場合は、背筋をまっすぐに伸ばし、肩を落として、肩の力を抜いてください。
目を閉じた方が気持ちいと思う方は、目を閉じてください。
息を吸い込んだときは静かにふくらみ、息を吐いたときは引っ込むのを感じながら、腹部に注意を集中してください。
息を吸い込んでいる間も、息を吐きだしている間も、呼吸のすべての瞬間に注意を集中してください。
自分の心が呼吸から離れたらことに気づいたら、そのたびに呼吸から注意をそらせたものは何かを確認してから、静かに腹部に注意を戻し、息が出たり入ったりするのを感じ取ってください。心が呼吸から離れてほかのことを考え始めるたびに、呼吸に注意を引き戻すのがあなたの仕事です。
どんなことに気を取られようともそのたびに注意を呼吸に引き戻してください。
このエクササイズを毎日都合のいい時間に15分行ってください。
気乗りがしなくてもとにかく1週間続け、生活の中に瞑想法を組み入れることによって、どんなふうに感じるか観察してください。
少しの時間でも、呼吸から意識がはなれることがあります。
急に歌のフレーズが思い浮かんだり、あれをやるのを忘れてた、こんなこのとやって効果があるのかなぁ・・・などなど、いろいろな考えがでてくることでしょう。
これは集中力がないからではありません。これは普通のことです。
いかに普段、今に集中していないことをおわかりいただけたでしょうか。
ストレスフルの方もそうでない方も、ぜひお試しくださいませ。

苦情をうったえても聞いてもらえない入居者はつらいはずです。
苦情を聞く側も辛いことですが、改善のきっかけを提供してくれているかもしれない、原因は自分たちにあるかもしれないということを考えながら、仕事として傾聴し、最後まで話をよく聞くことが最も大切な姿勢です。聞く側も、どうにもならない苦情の的になったときの辛さは、はかり知れないものです。
でもその経験は、他の人の助けになる優しさと強さを得ることができます。
試行錯誤しながらやれることはやって時を待つ、程よく上手に聞き流すコツを身に着ける、自分を責めない、自分をほめることを意識することが健やかに働く秘訣です。
しかし、どうにもならないときは、転職という選択肢もありです。その時はやりきった!と思って前向きな転職にしてほしいです。
まずは、自分を大切にして、そして入居者を大切にしていけるといいですね。応援しています。
次回は、介護予防についてお伝えする予定です。
📌老人ホームで働く管理栄養士の奮闘記 ~介護予防とレクリエーション~
まとめ
具体的な苦情まで、とても読み応えのある奮闘記でしたね。
私も特別養護老人ホームで勤務の際「特定の方だけに髪の毛が入ってしまう」苦情が続いていたことがありました。原因としてはご本人が頭を掻く癖があり、その際の抜けた髪だろうと施設側は言うのですが、ご本人とご家族は納得してくれず…管理栄養士として何度も報告や様々な対応に追われました。長谷川さんと同じく、施設側やケアワーカーは栄養課は悪くない、と一貫してかばってくれていたのでとても心強かったものです。勿論間違えていたことは謝らなければなりません。(異物混入でのクレームは数度経験があります。)これは後の経験になるというマインドはとても良いですね。しっかりと反省ときちんと謝罪をし、原因から学び、再発防止に努めることはきっと財産になるでしょう。
皆さんの参考になれば幸いです。
栄養士・管理栄養士の転職はDietitianJob!
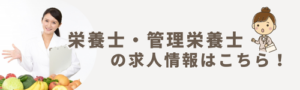
DietitianJob(ダイエッティシャン ジョブ)では、栄養士・管理栄養士の様々な求人を掲載しています。
あなたにあった働き方を一緒に探しませんか?弊社のエージェントは全員実務経験ありの栄養士・管理栄養士!
詳しいお仕事の話や、専門性のある質問にもお答えできるので転職後も安心!
弊社では、あなたの経験や強みを最大限に活かせるようにフォローし、理想の職場への転職をお手伝いします。
詳しくはこちらをご覧ください。
📌 関連記事<シリーズ全10回>










