
<最終更新2025.9.16>
こんにちは、管理栄養士の廣江です。
栄養士として現場で働いていると、切っても切れない関係の食物アレルギー。
アレルギーによるトラブルは知っていれば防げることがたくさんあります。
普段から保育園や学校を始めとした子供向けの大量調理に関わっている方はご存じのことが多いかもしれませんが、それ以外の方も是非栄養士として知っておきたい食物アレルギーの情報をお伝えします。今回は見た目はきれいでもアレルゲン物質は残っている…洗浄の話を実例と合わせてご紹介します。
📌 関連記事
第1回栄養士が知っておきたい食物アレルギー~おうち焼肉~
第2回栄養士が知っておきたい食物アレルギー~包装容器~
第3回栄養士が知っておきたい食物アレルギー~小麦粉~
第4回栄養士が知っておきたい食物アレルギー~ナッツ~
第6回栄養士が知っておきたい食物アレルギー~アレルギー表示~
目次
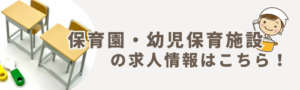
栄養士のアレルギー対応
食に携わる栄養士として、アレルギー対応は非常に責任の伴う仕事です。適切な対応、適切で安全な献立や食事を作るため、知識を深める必要があります。
そして、安全な食事環境を整えるためには一人ではなく調理員や職場により保育士、介護士、保護者とチームとなって対策を講じることは、対象者の健康を守るうえで欠かせません。今回は実例も紹介しながら、栄養士のアレルギー対応についてお話します。
食物アレルギーとは
改めて、食物アレルギーとは、本来無害である食物中のタンパク質に対して免疫系が過剰に反応し、皮膚症状や消化器症状、呼吸器症状などを引き起こす状態を指します。日本では小児の約5〜10%、成人の約2%前後に食物アレルギーがみられると報告されています(厚生労働省2023、日本小児アレルギー学会2022より)
免疫の過剰反応により、身体はさまざまな症状を引き起こします。例えば、皮膚のかゆみや発疹、消化不良、重篤な場合は呼吸困難等のアナフィラキシーショックなどが挙げられます。食物アレルギーは、個々の体質や遺伝的要因によって異なるため、同じ原因食品でも人によって反応や度合いは異なります。
また、主な食物アレルギーの原因食品としては、卵、牛乳、小麦、ナッツ類などがあり、特に子供に多く見られます。これらのアレルギーは、成長とともに改善される場合もありますが、大人になっても持続、または大人になって初めて発症することがあるため、注意が必要です。
子どもに多いイメージは皆さんあると思いますが、大人に多いアレルギー(甲殻類)や、高齢になっても継続している方ももちろんいます。特別養護老人ホームで管理栄養士を勤めていた際は、青魚のアレルギー対応がとても多かったです。昔は鮮度が保てずにサバ等のヒスタミンアレルギーが多かったのかもしれません。ご本人は一度起きたアレルギーがトラウマとなっており、青魚はそれ以降避けているというお話でした。
食物アレルギーの種類
・即時型アレルギー(IgE依存型)
摂取後、数分から2時間以内に症状が出現するタイプです。蕁麻疹、呼吸困難、アナフィラキシーなど重篤な症状を起こすこともあります。卵、牛乳、小麦、落花生、甲殻類(エビ・カニ)が代表的です。
・遅発型アレルギー(非IgE依存型)
症状の出現が数時間から数日後と遅れるタイプで、乳児の食物アレルギーに多くみられます。代表例として「食物蛋白誘発胃腸症候群(FPIES)」があります。下痢や嘔吐、体重増加不良など消化器症状が中心です。
・口腔アレルギー症候群(OAS)
果物や野菜を摂取した際に、口腔や咽頭にかゆみや腫れを感じるタイプです。花粉症に関連して発症することが多く、シラカバ花粉とリンゴ、スギ花粉とトマトなど「交差反応」が知られています。
食物アレルギーの原因食品
日本人における食物アレルギーの原因食品は鶏卵、牛乳、小麦が多く、長年、食物アレルギー原因食品の上位となっています。
ですが、近年はクルミやカシューナッツなどの木の実類のアレルギーも増えてきています。また、18歳以上では鶏卵は減り、小麦、エビ、カニが上位となります。
その他にも落花生(ピーナッツ)、キウイフルーツやバナナなどのフルーツ、イクラやたらこなどの魚卵、ソバ、大豆、魚類等多岐に渡ります。
アレルギーとわかっているなら、引き起こす可能性のある食材を徹底的に排除し、代替食品を活用すれば問題がない…そう思っていませんか?
今回は見た目はきれいでもアレルゲン物質は残っている…アレルギー対策と洗浄不足の話を実例と合わせてご解説頂きました。
その容器は本当にきれいでしょうか?

こんにちは。外部執筆スタッフ 管理栄養士のHOです。
食物アレルギーの対応はどうしても食品の原材料への注意が優先されがちです。
必ず洗剤とお湯で洗浄しているから大丈夫だと思われがちですが、
一見衛生的なようでも、アレルギー物質を取り除く洗浄ができていないことが原因で食物アレルギーの症状は起こる場合があります。
今回はAさんに起きた2つの体験談をもとに、注意点についてお伝えします。
Aさんは、卵や乳製品を食べると蕁麻疹や嘔吐、呼吸が苦しくなるアナフィラキシーショックの経験がある幼児です。
容器の洗浄不足によるアレルギーリスク

Aさんはイベントで、陶器の器で配られた豚汁(卵、乳不使用)を飲んだところ、しばらくすると顔全体に蕁麻疹がでてしまいました。
卵、乳不使用もしっかり確認したのにも関わらず…。近くの病院に搬送されて点滴等の処置も早かったので、大事に至りませんでした。
その後、原因は、豚汁が入っていた陶器のカップは、豚汁の前には、茶碗蒸しを盛り付けるのに使われていたことが判明。
なんと、温かい豚汁を入れたことで洗浄不十分で残留したものが溶けだしたものだ、と原因究明にいたりました。
イベントの際、大人には使い捨ての容器が使われていましたが、子ども用には大きかったため、小さめの持ち手のある陶器のスープカップが使われたのです。
使いやすさ重視で使用していたものの、まさか前回の茶わん蒸しで起こるとは思わず、チェック漏れが起きてしまったのです。
給食等でも器はコンタミネーションしないように注意を払っていることと思いますが、アレルギー反応は目に見えない少量から起こるもの。綺麗に見える器でもこうした危険につながるのです。
ランチョンマットで…!?

Aさんは自宅で卵や乳製品が入っていない昼食を食べたのに、しばらくすると口の周りが赤く腫れてかゆがりはじめました。
軽かったので手持ちの薬を使い症状は治まりました。…一体原因は何だったのでしょうか。自宅とはい言え、器は専用のものを使っていました。
なんと原因は……食器の下に敷いてあったランチョンマットだったのです。その角を口にくわえていたとお母さんの証言から判明しました。
Aさんのご家族は、器は別にしていたもののランチョンマットは家族共有で使い、洗濯していました。
しかし前日に弟が牛乳をこぼしたため、お母さんは、台所にあった中性洗剤をつけてお湯で洗い台所に干していたものをAさんに使ってしまったのです。
繊維の奥にまで浸透した牛乳が洗浄不足で残ったままだったと思われます。
普段、気を付けているお母さんでも、まさか口に入れるとは思わず、ちょっと目を離した間に起きた思いがけないことだったのです。
大人にとっては口にしないものでも、幼い子どもは予想外の行動をとるので環境整備と見守りの大切さを思い知らされました。

洗浄でのアレルギー対策
たんぱく質は30~40度のお湯で分解しますが、こびりついて時間が経った汚れは、浸漬時間が短いと汚れが落ちにくく、残りやすくなってしまいます。
また、ご飯粒などでんぷんが高温で糊状になり、冷めて低温になると水に溶けなくなり老化して固まると尚更落ちにくくなります。
たんぱく質の汚れも、でんぷんの汚れも洗浄の際は、シンクに20分以上浸漬してから洗浄するのが理想です。
もちろん、水より30~40度のお湯が最適です。大規模な施設では、浸漬用のシンクや温湯の自動洗浄機があると思いますが、自動洗浄だけでは残る場合もあります。
食器だけに限らず、箸やスプーン、鍋やザル、まな板などの調理用具や食事の際に利用する小物も30~40度のぬるま湯に20分の浸漬し、
スポンジで予洗いをしてから洗浄機に入れると除去力が高まり安心です。
洗剤は、アルカリ洗剤や重曹、セスキ炭酸ソーダなどを使用し、スポンジの共用は避けたいものです。
家庭と同レベルの小規模なところや、行事、災害時など、臨時設備などを使用する場合は、別に洗浄することが難しくなります。
また、短時間に片付けを行う必要があると浸漬が難しい場面も発生しますが、洗浄、乾燥、保管まで気を抜かない丁寧な作業と確認で安全を心がけたいものです。
まとめ
食物アレルギーは原材料だけでなく、器や布製品の洗浄不足でも症状が起こります。30〜40℃のお湯で20分以上浸漬し、器具や小物も徹底洗浄することが大切です。栄養士はチームで連携し、安全な食環境を守りましょう。
栄養士・管理栄養士の転職はDietitianJob!
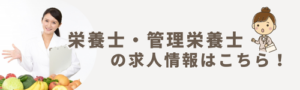
DietitianJob(ダイエッティシャン ジョブ)では、栄養士・管理栄養士の様々な求人を掲載しています。
あなたにあった働き方を一緒に探しませんか?弊社のエージェントは全員実務経験ありの栄養士・管理栄養士!
詳しいお仕事の話や、専門性のある質問にもお答えできるので転職後も安心!
弊社では、あなたの経験や強みを最大限に活かせるようにフォローし、理想の職場への転職をお手伝いします。
詳しくはこちらをご覧ください。










